![]() ホーム>サイト概要
ホーム>サイト概要
心理学を一緒にまなぶー 自己肯定感を育てる子育て…しないとだめですか?
![]() 作成日2021/5/1
作成日2021/5/1 ![]() 更新日
更新日
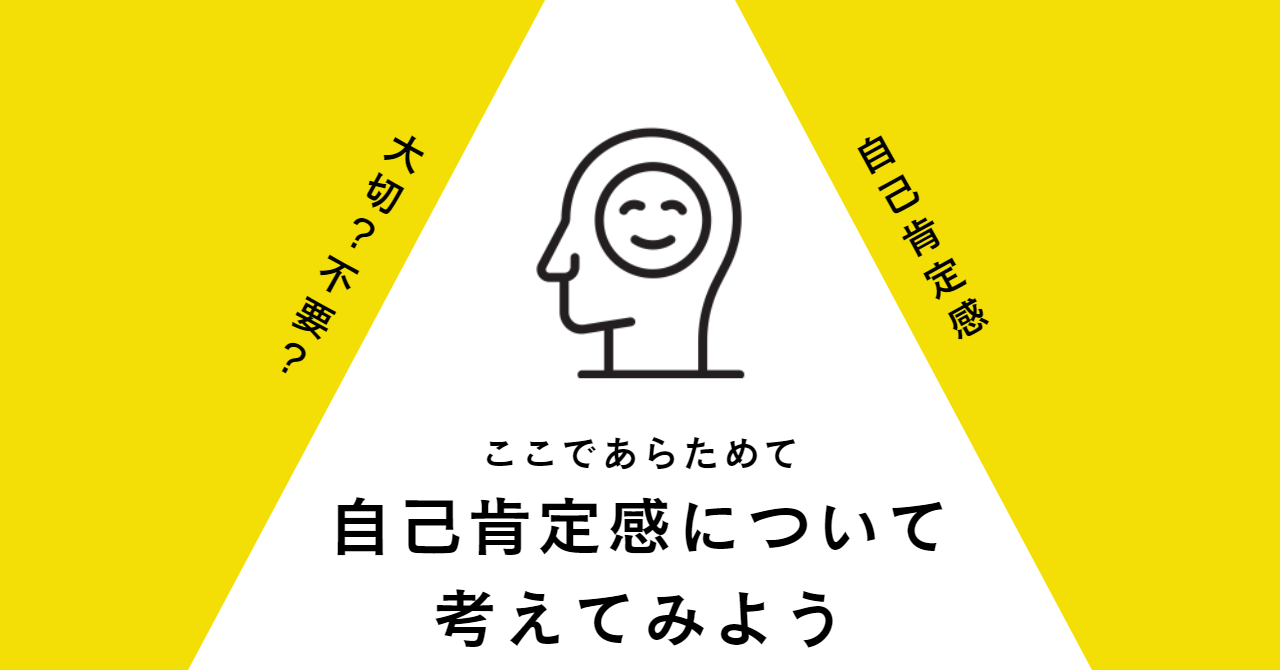
自分を好きでいることはいいことなの?
ここ10年の間、自己肯定感ブームと呼べるような自己肯定感にかかわる書籍の出版が相次ぎました。とりわけ家庭教育に関する書籍において自己肯定感を冠する書籍は多く存在します。
また、学校教育においても、子どもの自己肯定感の低さを問題視する教師は多く、子どもの自己肯定感をどのように高めるかという書籍は数多く出版されています(溝上,2020)。個人の肌感覚としては、もはや一過性の自己肯定感ブームは終わりをつげ、自己肯定感が高いことは良いことだ、当然だ、そのような空気があるのではないでしょうか。
人生における価値観は人それぞれであり、いいもわるいもないものですから、個人の価値観という観点から、自分が好きでいることがよいことなのか?と問うとするならば、その答えは「ない」というのが正解でしょう。
一方、心理学的な見方をするのであれば、自分を好きということ、自己肯定感が高いことが人生の成功や個人の幸福(ウェルビーイングということもあります)になにかしら肯定的な(プラスの)影響を与えているのだとすれば、自己肯定感が高いことはいいことであるといえるかもしれません。
自己肯定感が高い=よい とはいえないかも…
自己肯定感は学業成績と相関があるという研究結果もあるためか、学校教育においても高めるべき指標として扱われることが多い概念です。一方、近年では自己肯定感をやたらと強調することを疑問視する意見も出てきています。
たとえば溝上(2020)は、自己肯定感の高さと学業成績や心理的な適応とが関連している結果があることを認めたうえで、自己肯定感の高さの否定的な側面が報告されているにもかかわらず、自己肯定感を重視しすぎている現状を批判しています。
そして自己肯定感の否定的な側面として、たとえば競争的になりすぎて他人の気持ちを無視しやすい、失敗や批判を恐れ新しい経験を嫌う、ナルシズムの傾向を加えると侮辱された際に攻撃的になりやすい、などを挙げています。
また鹿毛(2022)も、自尊心(自己肯定感)の追及にはコストが伴うと指摘します。
わたしたちは自尊心を高めるために、(もしくは維持するために)成功を求めて努力しようとします。しかしその努力の中で、自己が崩壊したらどうしようという不安に脅かされるようになるというのです。そしてその結果、自尊心の低下を避けようと自分にとって都合の良い情報にだけ目を向けたり、現実をゆがめて解釈するようになるというわけです。
さらにひどい場合では、不正をはたらいてなんとか自尊心を満たそうとする-たとえばテストでひどい点をとって自尊心が壊れないように、カンニングを行うなど-こともあるといいます。このような自己肯定感を高めたり維持することで起こり得る負の行動が、「コスト」となるわけです。

それでは結局どうすりゃいいのか
それでは結局自己肯定感は高めた方がよいのか?とくに子どもの教育にかかわる教員の皆さんや親ごさんなどは気になってしまいますね。
結局のところ、自己肯定感は高ければいいってもんじゃない-という「なんだそれは!」とツッコミが入りそうなものが結論なのではないでしょうか。
鹿毛(2022)は、むしろいいところもあるし悪いところもある、それが自分なんだという自分を受け入れることができること(自己受容)が大切であると述べ、親や教師が子どもの自尊心を高めようとするあまり、過度にほめたり、ネガティブなフィードバックを避けようとする風潮を問題視しています。
たしかに現実的な場面を想像してみると、自己肯定感が高くともそれが他者の評価をともなっていない場合、(つまり自己肯定感は高いが周りの人は評価していないという状態のとき)それが望ましい状態といえるかは疑わしいと思います。
自己肯定感が子どもの育ちを見ていくうえで重要な概念であることは否定できません。しかし自己肯定感が高くなくてはいけないというメッセージばかりが声高に伝えられ、それにばかり囚われてしまう危険性が現在の育児、教育現場にはあり、その状況は変だといえるでしょう。
また、子育てや教育においては自己肯定感以外にも注視すべき様々な概念があるにもかかわらず、やたらに自己肯定感が強調される傾向があるのはなぜなのだろうと考えてしまいます。
自己肯定感ばかり目を向けるのではなく、もう少し幅広く子どもの育ちや学びを捉えていく必要があるように思います。自己肯定感に着目しているだけでは、子どもの育ちにおける、より大切なことを見落としてしまうのではないでしょうか。
子どもの気質によって自己肯定感に違いがあることは普通であり、たとえ自己肯定感が低い(と思われる)子どもであっても、それがとりわけ悪いことのようには思えません。自己肯定感が問題となるのは、自己肯定感の高低と不適応な行動が明らかに結びついている場合ではないでしょうか。
つまり自己肯定感の低下が、生活上における問題に影響を及ぼしていると認められた場合です。そうでない場合、子どもからすれば自己肯定感なんて意識しなくても楽しくやれているということもあるでしょう。にもかかわらず、やたらと周囲の大人が「自己肯定感は高めなければならない」、「自分を愛しなさい」というメッセージばかり与え続けることで、逆に子どもの心理的な負担が増大する可能性はないのでしょうか。
また自己肯定感は時や状況によって変動すると考えられ、自己肯定感が上がったり下がったりすることは、とりわけ思春期の子どもたちにおいては常々おこることであると思われます。
思春期においては友人や先輩と自分を比較することが多くなってくるため、そこで自分を嫌悪したりすることも起こりうる、それは普通のことです。そこで無理に自己を肯定して自己肯定感を短期的に上げることが望ましいとは思えません。
むしろ時間がかかっても、理想の自分と現実の自分とどう折り合いをつけていくのか、つまりどのように自己を形成していくのかが、自己肯定感の高低よりも重要なことであり、周りの大人が注視すべきことなのではないでしょうか。
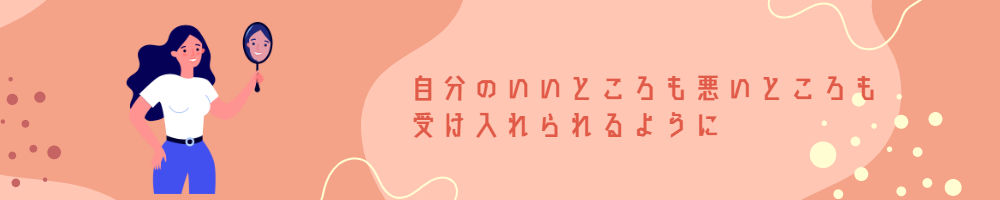
その結果、自己肯定感が高くなったということであればよかったよかったという話にはなるかもしれませんが、重要なのはその折り合いのプロセスであると考えられます。
参考文献リスト
溝上慎一 (2020). 『社会に生きる個性 自己と他者・拡張的パーソナリティ・エージェンシー』東信堂.
鹿毛雅治 (2022). 『モチベーションの心理学 「やる気」と「意欲」のメカニズム』中公新書
